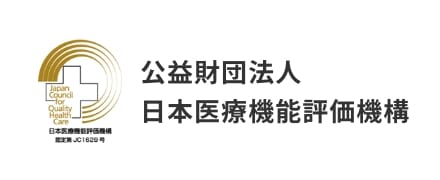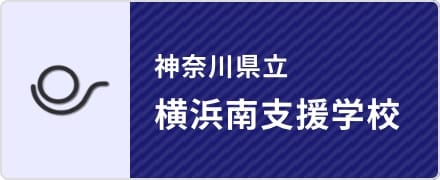緩和ケア普及室
概要
こども医療センターでは2008年に緩和ケア普及室の前身である緩和ケアサポートチームが発足し、その後2013年4月に緩和ケア普及室が開設されました。
私たちが掲げる「緩和ケア」とは、こども医療センターをご利用になるすべての子どもたちとそのご家族、これから生まれてくる子どもたちとその母親、ご家族に対して、自分たちらしく生きていけるように提供する、包括的かつ積極的な取り組みです。
「緩和ケア」を提供する実働部隊である緩和ケアサポートチームは、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床心理士、ソーシャル・ワーカー、ファシリティ・ドッグとハンドラーで構成され、それぞれの専門職を生かして子どもたちとそのご家族の苦痛緩和に対応しています。
緩和ケアサポートチーム
構成メンバー(2025年度4月時点)
緩和ケア普及室室長・専任医師(血液腫瘍科)、専従看護師(がん性疼痛看護認定看護師)、医師4名(身体的症状担当医師:血液腫瘍科・総合診療科、新生児科、精神的症症状担当医師:児童思春期精神科)、緩和ケア認定看護師2名、小児がん相談支援室看護師、薬剤師、臨床心理士、管理栄養士、ソーシャルワーカー、ファシリティドッグハンドラー、ファシリティドッグ
緩和ケアサポートチーム活動
- 病棟回診
- チームカンファレンス
- 関連診療科カンファレンス参加
緩和ケア外来
受診を希望をされる際は、当センターでおかかりの診療科主治医へ「緩和ケア外来」希望とお伝えください。
誰でも相談ができます。***一人で考えこまないでください***
・すべての疾患が対象です
・痛みだけではありません。どんな症状でもご相談ください。
・眠れていますか?イライラしていませんか?
・ごきょうだいが笑顔になる方法を考えます。
・ご家族が笑顔だとおこさんも笑顔になります。
気がかりはありませんか?お話をお聴きすることができます。
・おうちで過ごす方法を一緒に考えます。
・楽しく過ごすイベントを一緒に考えます。
小児緩和ケアセミナー
日常の活動から見えてきた課題からテーマを決め、その分野に詳しい方を講師としてお招きしセミナーを開催しています。日程は病院ホームページでお知らせします。
研究、発表へのご協力のお願い
緩和ケアサポートチームメンバーは、お子様とそのご家族が苦痛なく、その人らしく過ごすことができるために、日々努力しています。学会・研究会での発表や論文執筆により、他施設と情報を共有することで、よりよい医療やケアを提供できると考えております。そのために、日常提供している緩和医療・ケアの結果得られた医療情報を学術資料として使用させていただくことがあります。その際、個人情報管理には十分注意し、対応しております。発表、執筆に対しまして、みなさまのご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。ご不明な点がございましたら、遠慮なく緩和ケア普及室までお問い合わせください。